今日は雨だ。
いつまでも降る感じがする。
止まない雨はない。移り変わり。波。諸行無常。確かに世界は一瞬たりとも同じ瞬間なんてない。だけどこの心は永遠に思えた。
元々曇っていた僕の心。この旅をしていけば晴れると信じて、なんの根拠もないけれどただ歩いてきた。きっと太陽が見つかるだろうと。
だけど。彼女の死。それは雨を降らすには十分すぎるほどの低気圧だった。雲が集まり雨を降らす。どれくらい降るのだろう。涙は止まらなかった。
晴れて欲しいと願うほどに、嫌でも浮かんでくる雲のよう。彼女に対する罪の意識や、ロクでもない憶測、自分の情けなさや後悔が積乱雲をつくり続ける。
あんなに美しい彼女がどうして死ななくてはいけなかったのか。
どうして薄汚れた、何もない僕なんかが生きているのだろうか。
どうして僕は彼女を愛せなかったのか。
もう、僕の言葉を彼女に伝えることはできない。
いっそこのまま死んでしまえたら、もしかしたら彼女に会えるかもしれない。
そんなことまで浮かんでくる。
その夥しい量の思考や感情は浮かんでは消える、ことなどなく容赦無く積まれていき、めの前に真っ暗な雲が形作られていく。
体が重い。頭が痛い。胸が苦しい。もはや歩くどころか、立ち上がる気力もない。「生命とは動きだ」と彼は言った。なら僕はもう生命でないんじゃないか。木にもたれかかり、滝のように木を伝う雨粒を頭に受けながら、冷えていくはずの体温がいつもより熱いのを感じていた。
目の奥が重く、意識が薄れていく感覚。視界が狭まり、ぐわんぐわんと歪む。意識の狭間で僕はまた彼女を思い出して涙が頬から全身を伝った。
「なんで僕なんかと付き合ったの?」
純粋に疑問だった。それほどに彼女は僕とは正反対で、明るくて眩しかった。
彼女は首を傾げながら言う。
「うーん、理由なんてない、かな。というか言葉では表せないよ。磁石みたいなものじゃない?私は惹かれたの。感情はいろんな要素で湧いてくるし、その感覚に素直に従っただけ。もちろん優しいとか、趣味が合うとか、私を受け入れてくれるとか、顔が好みとか、言葉でも言えることはあるけど、それは一部であって、全部を言葉じゃ言えないの。車を分解していったとしてもそれで本質は見つからないよ。」
彼女は古代インドの思想家ナーガールジュナみたいなことを言った。照れ隠しと、彼女の独特な引用につい僕は笑ってしまう。女子大生でこんなことを言うのは彼女くらいじゃないか。
「つまり、君という存在自体に惹かれたの。要素はありすぎてわからないしそこに本質はない。だから、僕なんか…って存在を否定するけど、それは私にも失礼なんだからね。」
「ごめん…でも僕は自信がないんだ。君がそう言ってくれるのは本当に嬉しいけど、素直には受け取れないよ…だって僕にとって君の方が数百倍も素敵な人だ。釣り合ってるとは到底思えない。」
僕は言った後少し恥ずかしくて、胸のあたりが緊張し体温が上がるのを感じた。やっぱり彼女のことが好きだ。スタバでこんな話をする大学生は僕らくらいだろう。
「ふーん、ありがとう。そんなふうに思ってくれてたのは嬉しい。でも、私は君のことを私自身と同じくらい大切だと思ってる。だから卑下されると、嫌な気分になるよ。というわけで、そういうの禁止ね!」
「うわ、難しいなあ。」
「そういうところからだよ。簡単カンタン♪それとも何?これ以上か弱い私を傷つけるつもりなわけ?」
「はい。やります。カンタンデス。」
僕は明らかにぎこちなく、本音でなく答える。それを見透かして、半ば呆れながらも、彼女は笑顔で、
「それでよろしい。最初はね。」
彼女はよくわからないほどにカスタムされたフラペチーノ?を美味しそうに、笑顔で飲んだ。
僕は何のカスタムもしていないアイスコーヒーを手に取りストローを咥える。
ひんやりとしたはずの掌の感触と、流し込んだあとのコーヒーの余韻に、不思議と暖かさを感じた。
彼女がこんな僕を好きでいてくれるのなら、僕も僕自身を好きになれるような気がする。僕には磁石のような感覚はまだわからないけど、とにかく彼女といられるこの時間を、大切にしたいと思った。
彼女ならこんな状態の僕に対して何を言うだろう。
僕の存在を許してくれるだろうか。
愛していると確信できなかった僕を。
ひたすらに自分の中の自分は否定する。
「お前はクズだよ。愛しているがわからないなんて言い訳だ。自分を幸せにしてしまうことが怖かったんだろ。お前はずっと自分を否定することで存在できていたんだ。そのアイデンティティを壊そうとする彼女を恐れて、変わることを拒んだ。手を差し伸べてくれた彼女の手を跳ね除けたのはお前だ。そして彼女は死んで、お前はもう彼女の手をとることもないんだ。お前は自分を守った。彼女の想いを知りながらも踏みにじり、逃げてウジウジして、言葉で取り繕おうと必死になる。自分はこんなにも苦しんで、考えてるんだっていいながら許しを乞うているだけの哀れな偽善者。お前が死ねばよかったんだ。彼女を苦しめ、死に追いやった罪深いお前がな。」
僕は呻いた。この言葉も感情も、許してもらうために生み出している気がした。
もう彼女はいないのに。
「おい!こんなところにいたのかよ。探したぜ。」
返事もせず項垂れている僕の肩に彼は手を回す。
「さっさといかねえと風邪ひくぞ。近くに廃屋みたいなのがあったんだよ…っつうかアツっ!すでに熱あるだろ絶対。死にたいかもしれねぇけど、俺が死なせねぇから。迷惑だと思うかもしれんが、俺のわがままだ。」
「立ちたくない。死にたい。僕のせいだ…僕のせい。」
「アホか!あいつはそんなやわなやつじゃねえよ、って言ってほしいだけだろ。そういうのいいから。お前がお前のせいにしたいだけ。真実を突き止めに行くぞ。話はそれからだ。」
いつになくぼそっと言う彼もずぶ濡れで、眼は赤く腫れている。
雨は止む気配がなかった。







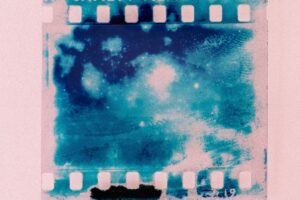







コメントを残す