「自然こそが神だよ。」
彼は言った。いや、僕はそう思った、の方が正しいかもしれない。街中を過ぎ、林を抜け、山とも言えない山道を歩く。日光浴を楽しむ草木も、爽やかな炭酸水みたいな川も、道端で勢いよく伸びる雑草や、庭に咲く整った向日葵やマリーゴールドも、美しく洗練されていて飽きなかった。だけど、それら全ては少なからず人の手により整頓された命だ。もしも人の介在しない形でしか本物の自然として存在できないとしたら、この世界、少なくとも地球上にはそんなところはほとんど残されていないかもしれない。たとえ残されていたとして、僕らが観測することでそれは自然とは違うものになってしまう、そんなジレンマの中に生きている気がする。人も自然の一部なのだと割り切ることができるなら、何もかもが自然の生み出した産物であるのだから、何もかもを内包してそれが自然だと言い切ることもできるはずだ。そんな、なんでも投げやりにしてしまうような主張にはなぜか違和感を覚えてしまうのだけど。
「まあ、人間はまだ自然に馴染んでいる途中なんだよ。長い目で見れば全てのものは自然という真理の設計図通りに収束する。人工物も時の流れにさらされることで磨かれて、自然な形に回帰するんだ。今は変化の早い、流れが激しい時代で、俺たちは原始時代と同じように環境に適応することを求められている。堰き止めて支配しようとした挙句、自分たちで生み出した大量の土砂に飲み込まれているのは全くの皮肉だけどな。」
結局、僕たちは自然から離れて生きていくことはできない。逆らったものは短い繁栄があってもすぐに淘汰されてエントロピーに消えていく。生き残るためには崩壊をなくすのではなく、最小限に細かく死を繰り返しながら変化していくしかない。僕は小さな崩壊の種を溜め込んで蓋をし、それによって生じた大きな洪水によって滅びかけたけど、なんとか乗り越えて今は生きている。歩いて、考えて、息をしている。なんとか適応しようともがいているちっぽけな命。いつかは消えてしまう儚い僕は、あの時なぜ死ななかったのだろう。なぜ生きているんだろう。まだ答えは出ない。答えなんてないのはわかっているけれど、どうせ生きるなら何か使い道を探したい。それに、誰かを愛し、愛されたい。生きている間にしか体験できないことをたくさんやらなくてはと執着している。欲望は醜い、のかもしれない。でも今はそんな自分が好きだった。
夜が近くなると人目に付き辛い場所にテントを張って、ランタンを灯す。キャンプ用のコンパクトなガスバーナーに火をつけて夕飯をつくり始めた。簡素な焚き火台は持っているけれど野営で焚き火をすることは厄介なことになりそうで憚られる。今はとにかく海を目指すことが目的なのだし、焚き火はできる時にすればいい。
「日本は規制ばっかりだし、人の目も厳しくて嫌になるよ。」
海外なんて行ったこともないのに独りごちる。正直なところ、この野営自体も法律に触れていないのか曖昧だ。他の国の事情もよく知らないし、今はどこもかしこもあまり自由ではないのかもしれなかった。だけど人生なんてのは、大きな流れの中にあって、どこに泳ぐかを選び取っていく自由しかないのだ。
クッカーに公園で汲んでおいた水を注ぎ、水分子が激しく動き出すのを待つ。道中コンビニエンスストアでいくつか買っておいたカップ麺から一つ選んで封を切る。今日はシーフードにしよう。こんなささやかな自由が心地よい。外の空気にさらされて食べるカップ麺はとても贅沢なものに感じるから不思議だ。例え人が手を加えた林の中であっても。それに……と不意になんだか腹落ちする感覚になる。木の一本一本は自然だ。人間という不自然にも振る舞う不確実なものに対応して生きている。それはある意味で自然への適応であって、強さの証明だ。隕石や氷河期を生き延びてきたのと同じように人間にも適応している。自然を心配するなんて、とてもじゃないが烏滸がましいことなんだ。詰まるところ僕らは、僕らの身の上を心配しているだけ。環境破壊は僕たち自身が生きるための環境を壊しているに過ぎない。宿主を殺してしまう癌や細菌になるのか、それとも腸内細菌やミトコンドリアみたいに調和して一緒に生きるのかを迫られている。でもどちらも人間にとって大事なだけで、より大きな視点では大した意味を持たない。人が何をしたって、時の流れを止めることはできないのだ。
気がつくと水は沸き立ち、一部の水分子たちはボコボコと空気中に散っていた。火を止めてカップ麺へ注ぎ込み蓋をする。閉じ込めた熱エネルギーは麺や具材へと浸透していくのだろう。スマホでタイマーをセットして目を閉じる。時は流れ、僕の心や思考は常に動き続ける。意図しようとしまいと。
朝早く撤収してまた歩き始める。比較的涼しいゴールデンタイム。ここ数日で随分と日焼けした。相当引きこもっていたツケを払わされて、僕の皮膚は唐突な日差しに適応できず容赦なく殺されていて、数多の水脹れがそれを物語っている。重たいバックパックを背負って歩くのも想像以上に体をボロボロにした。正直舐めていたし、若い体だと楽観視していたが、足の裏もところどころ皮が破れているし、筋肉痛もひどい。何かのイベントや誰かにやらされていたのならとっくに諦めていただろう。だけど僕にとってどうしても必要なことだった。巡礼の旅であり、修験道の修行のようであり、イニシエーションの儀式だ。他人にとっては無意味なことだけど、僕の中では彼女との約束であり、自分を信じるために何をおいても重要なこと。休み休みだけれど一歩ずつ着実に歩むのだ。きっとそれが生きることだから。



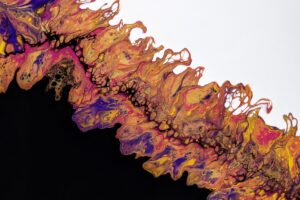




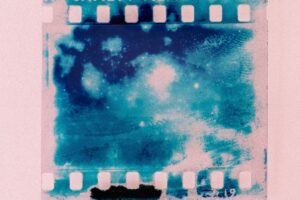











コメントを残す