今日は朝から雨が降っている。テントに弾ける雨音で目を覚ましたが、そういえばろくに天気予報も確認していなかった。一応レインコートは持ってきているが、バックパックをカバーするようなものは持ち合わせていないし、傘もない。その場しのぎに過ぎないけれど、貴重品や濡らしたくないものだけはコンビニの袋に詰めておく。ある程度の着替えやらは濡れるのを覚悟した方がよさそうだ。それに、テントだって地面の泥はねや水滴で汚れてしまったから、晴れた日にしっかり洗って乾かさなくてはいけない。想定していない面倒ごとは大抵の場合、ただの準備不足であることが多い。天を恨むのは筋違いだろう。それでも少しイラついた。そして「僕もイラついたりするんだな」となぜか少し安堵した。
運動靴はバックパックに無理やり詰め込んでサンダルを出す。黒い上下のレインコートをTシャツ短パンの上に重ね着し外に出ると、視界は飽和した水が空気中を漂って白くぼやけ、その中を慎ましく雨粒が通り抜けていく。そこまで大した雨ではないらしい。テント内よりはマシだが流石に長袖長ズボンは蒸し暑くて、結局ズボンも腕も裾を捲った。僕と接触し、摩擦によって速度を落とした雨が焼けた肌を伝うのは心地よかった。
濡れたままのテントを仕方なしに専用の袋に戻し、バックを雨ざらしにして歩を進める。先ほど天気を確認したところ、今日は一日雨のようだ。幸いなことに明日には上空の水は売り切れて支配権を太陽が取って代わるらしい。とはいえ、テントはさっき袋に閉じ込めたことで中まで濡れてしまったし、どこか宿を探さなくてはいけなかった。それに体は濡れてもいない内から水を含んだ砂みたいに硬まって重く、ドロドロと崩れ落ちそうだった。
「今日は温泉にでも入ってゆっくりしよう。」
自分を励ますように独りごつ。制汗シートだけでなんとか凌いできたのだが、3日ほどシャワーすらまともに浴びていない。ボロボロの体も労わってやらなくては。今は休めとお天道様も仰っている。
しかし休むにも一苦労だった。最寄りの温泉施設までは徒歩で2時間ほどとアプリ上では表記されていたが、5時間以上かかってようやくの到着。途中でコンビニに立ち寄って、バックパックを包める大きいビニール袋や、食料品と飲み物を買ったりと寄り道はいくらかしたものの、倍以上も時間がかかるとは思わなかった。想定以上に疲労が蓄積している。精魂尽き果てたとばかりに、到着してすぐに、枯れ枝がちょっとした風でひしゃげて折れるみたいに倒れ込む。入り口前のピロティにはベンチがあって、そこに座るだけの分別はギリギリ持ち合わせていた。バックパックを背中から引き剥がして一息つく。田舎ともベッドタウンとも呼べそうなこの街は入浴施設も宿泊施設も意外に多く、なんとか僕の一命を取り留めてくれた。今夜はこの温泉から徒歩圏内にある安いゲストハウスに泊まることにしたので、ひたすらここで長居して体力を少しでも回復させておこうと思う。それにしてもだ。
「ああ〜疲れた。」
ベンチで横になりながらため息混じりに漏らすと、意外なことに返事があった。
「随分とお疲れねぇ。」
驚いて顔を向けるとおばあさんが優しげな笑みを浮かべながら見下ろしていた。上品な身なりをしていて、背筋もまっすぐに伸びている。なんだか田舎の温泉には似合わない。疲れをわかってもらえた嬉しさと見られた気恥ずかしさをブレンドした感情のまま、なんとか無理やりに飛び起きて会話を続ける。
「日頃の運動不足が祟りまして……。」
「あらまあ。若いんだから体はきちんと動かさないと。日頃の小さな積み重ねですよ。」
「ぐうの音も出ません。ここ数日でいきなり体を動かしたので悲鳴をあげているみたいです。」
それから最近のことをつらつらと話した。主には野宿をしながら故郷の海まで歩いているこの数日のこと。
「ご苦労様ねえ。でも青春って感じ。戻ったらご両親には感謝を伝えなさいな。丈夫な体に生んでもらったんだから。」
「ええ……そう、ですね。」
僕が言い淀むとそれを察してかおばあさんは付け加える。
「過去に何があったにせよ、今は生きているんだから感謝だけは忘れてはダメよ。いいことも悪いことも全部が繋がって、今のあなたはできているんだから。」
「はい……確かにそうですね。この出会いにも意味がある気がします。ありがとうございます。」
「こちらこそ、老人のお話に付き合ってくれてありがとう。これはお礼よ。」
おばあさんは素朴だが品のある手提げ鞄から本を一冊取り出す。
「『グレープフルーツジュース』。読んだ事あるかしら?」
「あります。燃やしてしまいましたが……」
「あら、本当に燃やす人がいるなんてね。」
おばあさんは少し驚いた後、ふふふと口に手を当てて笑う。
「でも今は持っていないって事ならちょうど良いわね。旅のお守りで持っていって。」
「良いんですか?」
「私もちょうど燃やそうと思っていたところなの。」
「ふふ、そうなんですね。ありがとうございます。」
僕らは自然と笑っていた。文庫本を受け取って濡れないように貴重品袋にしまう。これも何か不思議な繋がりかもしれない。
「それじゃあ。旅路を頑張って。」
「ありがとうございました。」
おばあさんはもう温泉を後にするところだったらしく、駐車場へと傘をさして歩いて行った。人とまともに会話をしたのはいつぶりだろうなと思いながら、重い腰を上げて入浴へ向かう。今日は本当に疲れた。早く入ろう。
体を洗うとあちこちがヒリヒリと痛む。ただ焼きたてホヤホヤではないからか、なんとか我慢できる範囲だ。3日分の穢れを祓い清め、おずおずと湯船に浸かる。最初は「痛っ」とつい声に出てしまいながらも、ぬるめに調整されたお湯は一度浸かってしまえば天国だった。固まった繊維が解けていくように身体中の疲労がシュワシュワと音を立てて浄化されていく。「はあ〜」と普段は発さないような響きが自然と喉の奥からこぼれ、口からも疲れを吐き出しているかのようだった。ただ歩くだけなのに想像以上に骨が折れた。よくここまで来れたなと我ながら思う。特に今日は疲労のピークだったのか、痛みもひどく何度も心が折れそうになった。体の痛みと心の痛みは連動しているのか、道中は様々な暗くなるような思い出が想起されて、雨なのか涙なのかわからないけれど頬は常に濡れていた。
小さい頃の記憶。いつも他人が羨ましかった。ただ普通に笑って楽しそうにしている姿を見るたびに妬ましくて、そんな感情になる自分の浅ましさに嫌気がさす。僕は汚れている。濁った感情しか浮かんでこない。人間の出来損ないだ。苦しんでいる人や怒られている級友たちを見ると少しホッとしてしまう。いけないことだとは分かっているけれど、そういう気質だから仕方のないことなんだと諦めてもいた。皆みたいにうまく笑うことさえできない。失敗して引き攣った笑みを浮かべている自分しか想像できなくて、なるべくは無表情で居ようと努めた。自然な笑顔ができる人たちは眩しくて、僕はずっと下を向いて生きていた。目を合わせたら自分が劣等種であることがバレてしまう、そんな予感もトゲみたいに心を刺す。人の記憶から、この世界から消えてしまえればいい。だけど生きていた。ただ臆病だった。生きることに疲れて、自分という存在が恥ずかしくて、死にたい死にたいと願っていたけれど、死ぬには勇気が必要だ。電車に飛び込むことも、校舎の屋上から飛び降りることも、荒れた海へと沈むことも、包丁で自分を突き刺すことも、縄で首を吊ることも、実行に移す前に僕の体はコントロールを失って、ガタガタと音を立てて崩れるみたいに震え続けるだけで動かせなかった。たくさんの失望や恐怖や怒りが降り積もって、いつしか僕の体を埋め尽くしていた。
「助けて!助けてよ!誰か!」
よく夢を見た。僕は助けを呼んでいるけれど、その声はどこにも届いていない。
「お父さん!お母さん!」
誰も僕のことを見えていない。両親、先生、同級生、見知らぬ他人…たくさんの人たちは僕の存在に気づかず、幸せそうに過ごしている。それとも無視しているのだろうか。確かに、僕自身もどうやったら僕を助けられるのか、何をどうすれば良いのかさっぱりわからなかった。それでもただ苦しくて、呼吸ができなくて、泣き喚いた挙句、目を覚ますのは真夜中。きっと魘されて声は出ていたんだろうけれど、別の部屋で眠る両親は来ない。真っ暗な中でギュッとクタクタの布団を抱きしめながら、何も見ないで済みますようにと瞼にも同じようにギュッと力を込めて目を閉じた。今思えばむしろ来ないでくれて助かったのかもしれないけど。
露天風呂に移動して肩まで身を沈めながら、おばあさんの言葉を思い出す。こんな悪夢にも感謝できる日が来るんだろうか。僕は故郷で母親に会うんだろうか。痛みが少しずつ心地よさに変わっていく中でふと思う。降り積もった奥底に埋もれた微かな自分の声。助けてと叫んでいた僕は、きっと僕自身に助けて欲しかったんだと。世界をどう見るのかは全て僕に委ねられている。何もかもに絶望していたけれど、それはただ絶望を見ようとしていただけだ。レンズを曇らせていたのは自分で、世界はただの鏡にすぎない。自分を劣等種に仕立て上げていたのも僕だ。無理やりその証拠集めをしようと負の感情を集めていた。そしてそれこそが僕なんだとガラクタで彫刻を作り上げていた。
「僕は僕を救いたい。」
不意に浮かんできた言葉は胸の中を反響して、また僕は泣いていた。
「今までごめんね。」
声を必死に抑えて泣きながら目を開ける。まだ雨は降り止む気配はない。だけど。これだけ降ったんだから明日はきっと晴れる。そう確信した。

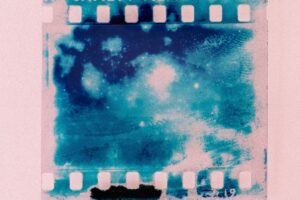


















コメントを残す