私は駆け出していた。冷め切った部屋の空気を脱ぎ捨てたくて、生ぬるい夜の闇へと。どうしようもない虚無感が押し寄せて、身体中にまとわりついて離れない。じっとりと湿った空気のせいなのか、汗と涙のせいなのかわからないけれど、飽和した水蒸気を全身に帯びているみたいに重たい。私は走っているのか、立ち止まっているのか、ここがどこで私が誰なのか、濡れてグチャグチャになった小説みたいにバラバラにほどけていきそうだった。
「どうやらダメだったみたいだな。」
いつからかわからないけれど、気づいたら彼がいた。
「これで良かったんだよ。この方がいくらかマトモだ。」
私は喉に鉛が詰まったみたいに声を絞り出す。
「私は、どうしたらいいのかな?」
ふぅーっと彼は一呼吸おいて答える。その口ぶりは妙に芝居がかっていた。
「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。」
「お邪魔しまーす!」
花火大会の夜、終電を逃した私は君の家に来ていた。ドアを開けると、熱が蓄積して膨張した空気がやっと逃げ口を見つけたかのように、モワッとした風が私たちを包む。スモークされるチーズみたいな気分だ。
「うわ、暑いね。冷房つけるよ。」
そう言い終わらないくらいにピッとリモコンの音が響く。私だけど。
「もうつけました〜!」
「スムーズすぎない?自分の家じゃあるまいし。」
「一度くれば大体覚えてるでしょ?」
私はリモコンを定位置に戻し、ベッドに腰掛ける。
「何か飲み物あるかな?」
「うーん。ビールならあったかな。ビールというか安い発泡酒だけど。」
冷蔵庫を覗き込み、350mlの発泡酒を2本取り出す。
「ここからは大人の時間だね。」
私は語尾にハートマークがついたような甘ったるい口調で投げかけるが、察しが悪い君は淡々としてうん、と返事をしただけだった。ポンポンとベッドの上を2回叩き、ここに座りなさいと合図をし、横に来た君と冷えた缶同士をぶつける。
「お疲れ!かんぱーい!」
「乾杯。」
プシュッ。カチン。ゴク。小気味良い音がリズムを刻み、私は締めとばかりにプハァーと吐息と声のミックスボイスを奏でる。
「夏は冷えたビールだねぇ。」
「女子大生というかおっさんみたいだよ。」
「私も気づけば21歳だもんね〜。しみじみするよ。」
私はまたグビグビと喉越しを楽しむ。
「反応するところそこじゃないでしょ。」
こんなやり取りが続き、お互いに1本ずつ飲み干した。お酒に弱い私たちにはちょうどいい量だ。酔いと夏の熱っぽさで火照った体が赤くなっている。
「夏ももう終わりだね。」
脈絡のない私の言葉に少し戸惑って間が開く。
「そうだね。」
文脈など関係なく続ける。
「付き合い始めてもうすぐ1年。そろそろさ……」
君の太ももにそっと手を触れ、肩をもたれかける。そして、少しビクッとして赤くなる耳元で囁く。
「しよ?」
なるべく艶っぽく伝える。どうせはぐらかそうとするのは目に見えているけれど。
「するって、何を?」
「もー!女の子にそれを言わせるのはダメでしょ。ねえこっち見て!」
恐る恐るといった動作でこちらを向く。私は浴衣をはだけ、じんわりと小麦色になりかけの肩が露わになる。そのまま浴衣をストンと落とすと君は明らかに動揺したが、ゴクリと生唾を飲み込む音が聞こえた。
「触って、いいよ。」
「いや、でも……」
言い訳が続きそうな声を遮るようにして捲し立てる。
「ゴムは君の財布に入ってるでしょ?」
「え、なんで……?」
テーブルの上に無造作に放り出された君の財布からコンドームを取り出して、証拠品だとばかりに目の前に突き出してぶらぶらする。
「そんなはず……」
「ほらね。君も男の端くれなら、据え膳食わぬは恥だよ?せっかく私が色っぽい雰囲気を演出したのになんだか興が削がれちゃったじゃん。」
はぁとため息を吐いて、足もベッドに乗るような姿勢で座り直す。泳いで逃げ出そうとする目をじっと見据えながら次の一手を打つ。
「そしたら、君が脱いで。」
「ちょっと待って……」
「だめ!それとも、私とはしたくないの?それならそう言ってよ。」
そう言うと泣きそうな目をしながらも、渋々といった様子でTシャツの縁で手をぎゅっと握る。深呼吸をして、一瞬覚悟が決まったような顔つきをしたがすぐに元の表情に戻っていた。そしてガタガタとベッドを揺らしながら震え始める。
「ぼ、僕には、無理、なんだ。」
震える声は途切れ途切れで、通信制限がかかってるみたいだ。
「ごめん。君のこ、とは好き、だし。僕だって、でも。」
涙と嗚咽が混じり始める。いよいよ通信状況は最悪だ。
「怖いの?」
「こ、わい。なんで、かわからない。ごめ、ん。」
「私こそ、ごめんね。」
私は浴衣を羽織り直すと、肩を抱き寄せて頭を撫でる。気づけば私の目からも涙がこぼれ落ちていた。
「私のこと、愛してる?」
「わからない。僕には。ごめん……」
私は君から離れて手で顔を覆っていた。
「きっと、僕は、君を愛していないんだ。」
その声を聞くと、熱を帯びた涙腺は決壊した。2度と元には戻らない。そんな気がした。しばらく二人して泣いていた。私の涙はなんなのだろう。私とはなんだったのだろう。君の心は最後まで許してくれなかった。思考が延々と行ったり来たりを繰り返し、どれくらいの時間が経っているのかわからなくなる。もう仕方がない。何度もそう言い聞かせたけど、なかなか言葉にならない。諦めるしかないのかな。ごめんね。今までありがとう。浮かんでくる色んな言葉を飲み込んで、冷たく言い放った。
「愛していない、なら、君と一緒に過ごした時間には何の価値もなくなる。私は君を愛していたけれど、それは独りよがりな自分の快楽でしかなくなるの。」
君は俯いたままだった顔を上げて、そうじゃないと言いたげな苦しそうな表情をしたけど、終わりを察していたのか何も言わなかった。
「さようなら。」
君が潔くいられるようにと願い、諦めと嘲りを精一杯に捏造して一瞥をくれると、私は部屋を出ていく。夏は終わっていきなり冬が来たみたいだった。この扉の先に行くあてはない。死に場所以外には。
私の物語は終わる。
役割を終えたキャラクターは舞台に上がることはない。
これが喜劇なのか悲劇なのかも知らないままに。




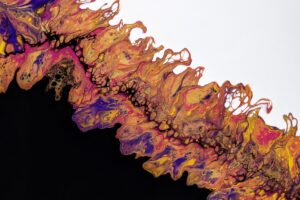















コメントを残す