「私が生まれたのは、ほんの最近のこと。初めて君の前に出たのはキャンプの時ね。」
彼女は僕の知っている彼女ではないようだった。快活で陽気な雰囲気は失われ、口調には冷んやりとした印象を受ける。彼女も僕自身が生み出した幻想だ。頭ではわかっているつもりでも、感覚的な理解ではない。僕の脳が生み出した理想のパートナーとでも言うのだろうか。なぜ僕は彼女を生み出したのか、本当のところはまだ何もわからなかった。
「私の役割はシンプルに君の心を開くこと。そのための触媒とでも言うのかしら。真実に気づき、本当の意味で人生を生きるために必要だったの。君には、主観的に外部からだとしか思えない、鍵となるような存在として。」
僕はただ黙って聞いていた。彼女の言葉は僕自身の言葉であるはずなのに、どうにもよそよそしく感じられて実感が湧かない。頭の中で反芻する。心を開くこと。その触媒。真実に気づくこと。彼女と過ごした時間はまやかしだった。ずっと訳がわからないはずなのに、それが事実だと悟っている感覚。自覚こそしていないが知っていたんだ。本当はずっと。
「だけど私には扉を開けることはできなかったの。最後に開けるのは君自身しかいない。わかってはいたけれど、寂しかった。一緒に生きることができると思っていたの。でも、失敗した。」
儚げに、自嘲気味に、彼女は微かな笑みを浮かべて、後悔と寂寥感が胸に込み上げる。僕は彼女に「愛している」と言うことが出来なかった。あざだらけの体を見せることすら怖くて震えて、受け入れてもらえるはずだと頭では、いつも頭ではわかっている。幻想であっても彼女は僕にとってかけがえのない存在で本当は愛していた。でもそんな自分自身を信頼できなかったんだ。いつだって疑いの言葉が自分を縛り付ける。「これが愛なのか?お前が愛を感じられるのか?どうせ裏切るに決まってる。失望させて、怯えさせて、汚してしまうのがオチだ。」自分には愛される価値も、愛する資格もないのだと言い聞かせて、そんな自己像をせっせと築き上げていた。涙はずっと止めどなく頬をつたっている。彼女は数秒の間をおいて囁くように続けた。
「だから、死んだの。死というものを通して、ようやく君はここまで辿り着くことができた。だから結果的には成功ね。私は幽霊だけれど、元から幽霊みたいなものなのだし。」
「ごめん、本当にごめん。今更、許されないのはわかってる。こんな、死ぬような真似をしたって、何にもならないのも。でも、でも、どうしたらいいか、わからなかったんだ。」
「許すも許さないもねえよ。この世には善悪もないんだ。全部、お前のでっちあげだよ。だからさ、お前自身で決めろよ。どうしたいんだ?」
「許してほしい。ごめん。いや、ありがとう。愛してるんだ。」
しゃくりあげて所々つっかえながら叫んだ。謝りたかった。こんなに分からずやな僕をずっと見守っていたことに対して感謝したかった。どちらも本音だった。彼女は、彼は、僕の一部なのだ。幽霊でも、幻想でも、僕の大切な一部で、僕自身だ。
その瞬間、全てがつながった様な感覚に襲われる。頭が真っ白な光に包まれる、そんな感覚だ。そうだ……僕は僕を許し、愛したかった。彼や彼女の望みは、僕が潜在的に欲していたこと。彼らは理想でありながら僕自身でもある。僕の中に存在していたのだ。そんなものは持ち合わせていないと思い込んでいた、愛や、思いやりや、強さや、溌剌さや、行動力は確かに僕の中に存在している。彼らは僕自身なのだから。本当はずっと僕の中に居たのに、否定し続けていた自分。そんなものは無いと決めつけて諦めていたつもりだったけれど、ずっと本当はどう生きたいのか教えてくれていたのだ。
「僕はずっと君らを否定し続けた。僕は穢れた罪人だから、君らみたいに生きられるはずがないと思い込んだ。だけど、本当は、本当は……」
いつの間にか口をついて声になっていた。鼻を啜り、咽びながら、唐突に温かい感覚に包まれる。彼女は僕に抱きついて泣いていた。さっきまでの冷え切って死んだような声じゃなく、ちゃんと生きている。僕も彼女を抱きしめて泣いていた。それを見て彼は満足そうに微笑んでいる。
「僕は生きたい。僕自身を愛して、人を愛したい。それができるって信じたい。いや、信じるよ。僕の中には確かに全部あったんだ。」
「ま、そういうことだな。今までは全部お前の一人芝居だった。お前が脚本演出で監督で主演だよ。バカみたいだろ?これからどうするかもお前次第さ。俺たちは文字通り舞台から降りるよ。あー疲れた。」
「だけど私たちは君自身だから、いつだって一緒だとも言えるけどね!でも、そろそろ現実の今を生きる時だよ。目を覚ます時だ!少年!なんてね!ふふっ。」
満足そうに笑う3人、いや厳密には僕。目一杯泣き腫らして顔を上げると、雨あがりの艶やかな木々やスッキリとした青空を眺めたように、爽快な気分でこんな感覚は久しぶりだった。いや、初めてかもしれない。そして、霧が晴れると同時に彼らは消えていた。寂しさも虚しさも少し感じるけれど、視界は澄み渡って、重くて苦しかった体も余計な力が抜け落ちたように軽い。全てが夢幻だった。だけど全てが僕にとっては真実だった。

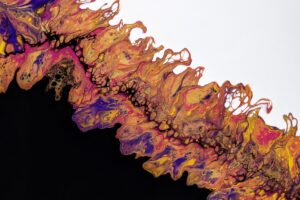


















コメントを残す