「あのさ!」
一瞬の緊張を悟らせないようにと声を掛ける。君は珍しい動物でも見るように驚きと好奇心で満ちた目で私に向き直る。
「何、かな?」
「もうちょっと海風を浴びてたいなって。あっちは砂浜じゃなくて岩場になってるんだけど、多分景色も綺麗だと思うんだ。行かない?」
「そうなんだ、せっかくだし見ておこうかな。」
胸の内で小さく喜ぶ。最初のミッションは達成だ。後ろから一人歩く彼を一瞥すると、お願いした通りの返答をくれる。
「あ、俺はそろそろ帰るから。予定あんだよね〜。二人で楽しんでけよ。」
グッジョブ!という思いを込めた目配せをすると、彼は片方の口角をあげて呆れたように笑う。
「そうなんだ!残念!写真は送るから!お言葉に甘えていこっか!」
私は心にもないとバレバレな残念を残し、君に有無を言わせない内にその手を引っ張る。
「え?ちょ、ちょっと……」
動揺を隠しきれていない様子が可愛い、なんて少し笑いながら、はたから見るとあからさまな行動に出る。これくらいしてようやく意識してくれるだろう。彼には後でお礼をしなくちゃなとも勿論思いながら、私たちは岩場へと走った。
「あそこからの眺めもなかなか良さそうじゃない?」
「うん。」
走ったからなのか、すっかり明るくなった光の加減なのかはわからないが、君の顔が紅潮しているように見えた。私も赤いのだろうな、と思いながらその顔を隠すように俯きながらしゃがみ、手に持っていたビーチサンダルを履く。ゴツゴツした手触りを感じながら岩を少し登ってみると、太平洋からすっかり全身を露わにした太陽がキラキラと水面を照らす。岩が多い地形だからか波の崩れ方が砂浜とは異なるようで、白波がそこかしこに彩りを添えていた。
「ここからの眺めすごい綺麗。上に来てみて!ちょうどここ座れそうだし。」
私が笑顔で呼びかけると、意外とすんなりとした足取りで隣に腰を下ろす。
「確かに綺麗だね。」
波音にかき消されそうにこぼす言葉からは思ったよりも感動が伝わってくる。よかった、と安堵の笑みを浮かべるがここからが本番だ。しばらくは見とれて言葉も交わさずに佇む。さて、と私が声をかけようとすると意外にも君の方から話しかけてくる。
「なんかさ、なんでかわからないけど懐かしい感じがするんだ。海から日の出を見るなんて、全然したことないのに。」
「きっと日本人の魂に刻み込まれてるんじゃないかな〜。魂というかDNAというか?」
「確かに。記憶にあるだけが懐かしさの要因というわけじゃないのかも。」
「うんうん。記憶よりももっと奥の方の心が動く感じするよね!だから自然と触れ合わないとだよー!」
「そうだね、焚き火とかも、昔から人類にとって大切だったんだろうね。」
「間違いなし!ずっと見てられるもん。」
話が思ったよりも弾んで嬉しくなる。こういう感覚は人間誰しも持っているはず。だからわざわざ都会を離れてキャンプをするのだろう。やっぱり自然の力は偉大で、心を開かせてくれるきっかけには十分なのだ。
そうしてしばらくの間私たち二人はピカピカに眩しい太陽を眼前に話し込んでいた。朝の涼しげな空気が打って変わって、だんだんと湿気を帯びたジリジリとひり付く粘っこい感覚にグラデーションを移す。そろそろ戻ろうか、と口を開きかけた瞬間、甲高くもどこかで聞き覚えのあるチャイムが鳴った。
「7時だね!そろそろ戻ろうか〜?」
「そうだね。暑くなってきたし。」
ツバの広いストローハットをかぶり、ちゃっかり持ってきていたサングラスをしている私と対照的に、君はTシャツに長いジーンズとスニーカーという海には似つかわしくないような格好をしている。僕も帽子とか持ってくるんだった、と呟きながら気怠そうに立ち上がると眩しそうに目を細めながら小さく伸びをした。
「本当に、TPOをもうちょっと弁えた格好をしましょうね。」
そういうところが可愛いところでもあるんだけど、という言葉は胸にしまいつつ畏まった冗談くさいセリフを吐く。そうだね、と自嘲的に笑いながら岩場を降りていくが、インドア派に似合わずヒョイヒョイと軽い足取りだ。
「ちょっと、手を貸してくださる?ジェントルマン?」
さっきのキャラを継続して気取った風に声をかけると、照れくさそうにしながらも一瞬迷って手を差し出してくれた。
「はい、お嬢様。」
思っていたよりノリの良い返事に満足しつつ、お互いの汗と潮風で湿った手が触れ合ってドキリと心臓が締め付けられる。そうやって手を取り合って岩を降りると、まるで悪いことをしてしまったとばかりそそくさと君は手を離した。明らかに動揺しているのを尻目に何でもないことのようにじゃあ帰ろっか、と元気よく笑顔を向ける。うん、と波音に負けるくらいのか細い声で返し、下を向きながら歩き出した。
砂浜を歩き始めて数分。私たちは言葉も発さずに足跡を上塗りしていた。私自身はこの後のことを考えて緊張していたのだが、君はさっき手を握った時のまま恥ずかしそうにしている。スゥーっと深く息を吸い、意を決して声をかけた。
「ねえ!伝えたいことがあるんだけどさ!」
声を振るわせないようにと大きな声を出してしまい、君はビクリと目を見開いて横にいる私に向き直る。驚いたまま小さく何度か頷きながら先を促され、私は続ける。
「実は君のことが好き、なんだ。付きあってください!」
ザバーンッと波が飛沫を上げて弾ける。まっすぐに目を見つめる私から発せられた言葉に、少しの間は理解が追いついていないように呆気に取られ沈黙が場を満たす。理解が追いつくと同時に、そんなことを言われるなんて夢にも思わなかったとばかりに「え、え、えと」と頭を掻きながら目をパチクリさせていた。こちらとしてはあまりに予想通りの反応に緊張を忘れ笑ってしまう。数秒のパニックの後、なんとか落ち着いた答えが返ってくる。
「えっと、その、僕なんかでよかったら、お願いします。」
私はそっと手を握る。握り返された手のひらはさっきよりもお互い湿り気と熱を帯びていた。顔は日焼けのせいも相まってか真っ赤に染まっている。砂浜を歩く二人を太陽は煌々と照らし、心地よい海風が背中から吹き抜けた。
こうして私たちは付き合うことになる。まあ最初から決まっていた出来レースではあったのだけど。だって私は君の全てを知っているから。私は君を愛するために生まれたと言っても過言ではないのだから。でも君は知らないのだろう。いや、知っていて見ないふりをしているだけかもしれない。深く閉ざされていて、誰にも、自分にもひた隠しにしているその奥底。私は……



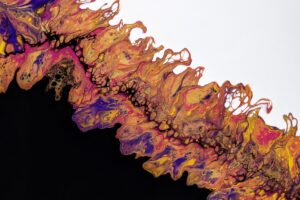


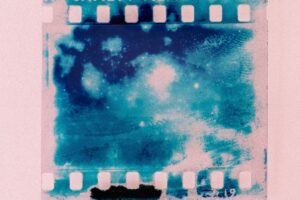







コメントを残す