「海だ!」
僕は思わず声に出していた。やっと辿り着いた。幼少期に見た馴染みのある風景に、思い出したくもない過去も、なんでもない思い出も、たくさんの感情も同時に浮かんできて、それらを懐かしさがそっと包んでいる。故郷の海。平日とはいえ夏休み期間だからか、家族連れの姿もちらほら見かける。この砂浜はきちんとした身なりの観光地ではない。それは今でも変わらず素朴で落ち着いた雰囲気を放っているけれど、押し寄せる波は力強く、子供なら簡単に飲み込んでしまうような厳しさも醸し出している。照りつける日差しをゆらゆらと乱反射した海は、一見穏やかで爽やかな表情だが、荒々しい一面を隠そうともせず両立しており妙に清々しい気分にさせる。
僕は背負っていたバックパックを砂の上に投げ出して、自由になった背中と腕で大きく伸びをする。真夏の温みと湿り気を帯びた空気をめいっぱい吸い込んで、磯の香りと塩辛さを全身に染み込ませていく。吐き出す空気とともに声が漏れて、疲れがどっと押し寄せる。腕に押し除けられた帽子がやっと僕も休憩だとばかりにバックパックのそばに落ちた。汗でびっしょりした気持ちのいいとはいえない靴と靴下を脱いで、砂浜に寝そべると、太陽のエネルギーを溜め込んだ砂の粒たちによって一瞬は身が焼かれるようだった。だけどその熱はいつの間にか僕の体に取り込まれ、均されて、溶けていく。眼前のあまりに強い太陽を遮るように、瞑った目を手で覆いながら一息ついた。この10日ほど、長いような、短いような道のりだった。
家の中ですら、僕の知らないことが多かった。いつから押し入れの中に仕舞われていたのかわからない大きなバックパックやキャンプグッズに、買った覚えのない本の山。どれだけ狭い視野で、定型のルーティンの中で僕の暮らしは成り立っていたのかと考えると我ながら呆れる。見たいものだけを見て生きてきた、いや、なるべくは何も見ないように、気が付かないように生きてきたのだと。どれだけのことを見落として、見殺しにして、無かったことにしようとしてきたのか。鬱々とした気持ちが込み上げてくるのを必死になって見守る。それを受け入れるしかないんだ。これからはありのままに、自分の心も世界も見ていくのだと決めたのだから。そして、僕は歩くことにした。とにかく海へ。自分の生まれ育った街へ。やめてしまった旅を再開して、海風を浴びるのだ。
思い立ったが吉日、いや吉秒とばかりにバックパックにそそくさと服やらキャンプグッズを詰め込む。何に追われるわけでもないのに、ほんの十数分で準備を終え自宅を出た。何を持っていけばいいのか分からないけれど、どうせ確かな答えなんてない。とにかくこの心に従うんだ。人生は極論、それしかないのかもしれない。2時間前には死のうと決意していたはずなのに、今は特段の意味もなく遠い道のりを歩こうとしているのが自分でも不思議で、なぜか当然のように感じた。
最初は見慣れたはずの景色。だけど普段は気にも留めなかった道のあれこれが目に入ってくる。
「こんなところに神社なんてあったのか!何を祀ってるんだ?」
「この家のポストはこんなところにあったっけ?」
「この店の看板ってこんな色をしていたっけ?」
何もかもがゲシュタルト崩壊を起こして、揺らいでいて、不確かで新しかった。住宅地を離れて山あいの道を進み出すと、夏の日差しを浴びて生き生きとした植物たちに自然と視線が吸い込まれる。ああ、生きているんだな、と当たり前のことをさも新鮮なことのように思い出す。当たり前というのは恐ろしいもので、本当はなに一つ同じものなんてないのに、全てを同じ色で塗りたくってしまう。長らく僕の絵の具は黒一色しかなくて、塗りつぶしては見えなくしてしまったんじゃないだろうか。『クレヨンのくろくん』という絵本では最後に表面の黒を削って鮮やかな花火を描いていたっけ。遠い昔に読んだはずなのにそのシーンだけはハッキリと覚えている。そして、思い出して目が潤む。去年の花火も綺麗だった。あれは僕一人で見ていたんだなと考えると気恥ずかしさと寂しさも感じるけれど、それでも花火は美しくて、彼女も美しかった。彼女も僕なのだから僕自身にも美しさがあったんだな、なんて照れ臭い考えが浮かんだけど、胸の奥がじんわりと熱くなる。じっとりとした外からの熱じゃなくて、内側から滲み出るような何処かほっとする暖かさだった。



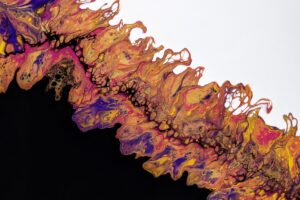


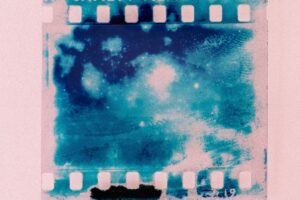








コメントを残す