首吊り自殺は簡単らしい。確かにロープ一本で逝けるのだからありがたい話だ。僕の部屋のアパートには天井に引っ掛けるようなとっかかりはないけれど、調べたところ、どうやらドアノブなんかで良いらしい。それに、タオルとかコードなんかでも実行可能とのことだ。
ふとドアノブにぶら下がる自分を想像してなんとなく格好悪いと感じる。死ぬんだからそんな体裁なんてどうでも良いことなんだけど、僕はそれを気にするくらいには余裕があると言うことなんだろう。本当に悩み抜いて死を決断した人たちに比べて自分が劣っているような気がする。僕だって僕なりには悩み抜いた。それに、未来に希望は見えなかった。どこまでいっても僕に幸福はきっと感じられないだろう。僕は僕を許せないだろう。死ぬことで許せるのかと言えば難しいけれど、生きてるよりはいくらかマシだ。本音を言えば逃げたいだけ、かもしれない。わかっている。なんて僕はダサい人間なんだろう。全てからただ逃げる。逃げちゃダメなわけじゃない。最後のこの決断くらいは大事にしてあげよう。さあ、死のう。潔く。武士道とは死ぬことと見つけたり。武士とは程遠い生き方だったな。
どれくらいの間、行くあてもない思考の旅路に出ていたのかわからないが、ようやく重い腰を上げる。僕は買ってきていたロープを結んで円を作り、トイレのドアノブにかけた。これで本当に死ねるんだろうか?思った以上に低くなってしまった首吊り台で試行錯誤する。座ったままだと難しそうだ。結論、うつ伏せで眠るような形で実行することにした。また、トイレのドアだとうつ伏せになれるスペースがないので、自室のドアで行う。死ねるのかどうかは正直よくわからない。
「こんなにあっさりと人は死ねるのか。いつでも死ねるじゃないか。」
そう思うと、今じゃなくても良いんじゃないかと、生へしがみつきたい欲求にも駆られる。無様なものだ。
準備は整った。あとは遺書を公開し、死ぬだけだ。警察には届け出ないでおこう。早めに見つかって死ねなかった時に色々と面倒だ。苦しみから解放される。もう起き上がらなくていい。なんて楽なんだろう。少しの喜びを久々に感じた。皮肉なものだ。笑みを漏らしながらロープを首にかける。あとは手も足も力を抜いて、首だけでぶら下がればいい。途端に、猛烈な恐怖感が心を波立たせる。
「黙れ!」
僕は声を荒らげる。自分に何度失望させられるのだろうか。震え始めた手。唐突に涙が溢れ、頭痛がしてくる。ズキンズキンと心臓の鼓動に合わせて痛みがこめかみを締め付ける。
「俺の声を聞け!」
本能の訴えだろうか。そう言って激しく僕の中を暴れ回っている。胸は付けられたように苦しく、お腹も緊張して強張っている。心臓が早鐘を打ち、心をノックし続ける。
「死なせてくれよ!」
喘ぎ喘ぎ自分に言い聞かせる。どこまでいっても僕は僕なのだ。死ぬことすらまともにできない。心底嫌になる。何が僕を生に執着させるんだろう。なんの価値もないのに。何も思い残すことなんてないじゃないか。生きる意味も、愛も、幸せも、僕には感じることができない。人間として大事なものが欠けているんだ。僕が普通に愛を感じられたなら、彼女を死なせずに済んだかもしれないのに。
「なんで、なんで……」
謎だった。死なない理由なんかない。なんで僕の体は生きようとしているのか。なんでこんなに苦しいのか。
「答えが知りたいか?」
ハッキリとした声が響く。自分の声だろうか?いや、違う。この声は……。痛みと震えでクラクラしながら、振り返って部屋の中を見ると彼が居た。
「お前、すげえ顔してんぞ。若きウェルテル君。」
彼はいつになく楽しそうに笑いながら僕を見下ろしている。パニックだった。ありえない。なんで彼がここにいるんだ?どこからどうやって入ったんだ?さっきのは彼の声か?何が何だかわからない。
「何が何だかわからないって顔だな。」
心を見透かしたように彼は続ける。
「察しが悪すぎて呆れるよ。どれだけ自己欺瞞を重ねれば気が済むんだ?」
何を言われているのかさっぱりわからない。いや、微かにどこか胸の奥底で違和感のような感覚を覚える。
「お前は何も知らないまま死ぬのか?真実を知りたくないのか?」
真実って何のことだ。彼女の死の真相か?僕は声を絞り出そうとするが、体の震えと反対に声帯は震えを通さないようだった。
「彼女の死。それだけじゃない。俺について、そしてお前自身、この世界についてだ。」
彼は舞台役者のように身振り手振りを交えながら語りかけてくる。理解できないけれど体の震えや痛みは止まらなかった。
「さあ選べ。赤いピルか青いピルか。」
これは走馬灯に違いない。死ぬ前に潜在意識が痛烈に反応して呼び起こす幻覚の類だ。もうすぐ死ねるに違いない。そうに決まってる。あまりにも現実離れした目の前の出来事は、不思議なことに夢の中のような現実感を伴っていた。
「アンダーソン君。いやネオ。まさかマトリックスを知らないわけはないよな?」
知っていた。大好きな映画だ。赤いピルを飲めば真実に。青いピルを飲めばマトリックスの中に戻される。でも僕は救世主なんかじゃない。これから死のうとする人間だ。彼は頭がおかしい。いや、これは僕が生み出している幻。そう、僕が壊れているんだ。僕は震える手を差し出す。膝をついて息も絶え絶えに薬を欲する様はドラッグ中毒者みたいだった。
「赤い、ピルを、くれ。」
どうせ死ぬんだから真実とやらを知りたい。そう思った。でも彼に近づくにつれて鼓動は早まり、震えと痛みは増していく。「知ってしまったらもう後戻りできない。僕という存在そのものが崩れ去る。やめておけ。」そんな直感が働く。でも別に僕なんて崩れ去ればいい。磔にして殺してしまえばいい。どうせ殺そうと思ってたところだ。ちょうど良いじゃないか。諦めにも似た感覚が心を軽くした。
「さあ、いよいよ真実を知る時だ。物語も大詰め。楽しい伏線回収の時間だよ!よくここまで辿り着いた。飲み込め!」
彼はいよいよクライマックスとばかりに楽しそうに僕にピルを手渡す。真っ赤なそれを噛み砕くと、視界が一気に開けたような感覚に陥る。瞬間、僕の中に恐ろしいまでの情報が流れ込んできたように、物事が飲み込めてくる。
「やっと思い出したか?本当に長かったぜ。」
僕は思い出していた。押し込めていた蓋が開いたように次々と。ゼウスが与えたパンドラの箱が脳裏によぎる。目を背けてきたあらゆる不幸や災いが入っている箱。今までの苦しみなんか序の口だったのだ。あんなものはただの被害妄想で、この箱の中身こそが真実。そう確信させる鮮明な記憶だった。発狂して走り出したい気持ちを抑えて情報を整理する。
「まあ、俺の話は俺から語るとするか。その方がわかりやすいだろう。」
誰への配慮かわからないが、彼は語り始めた。彼の過去。そして真実を。





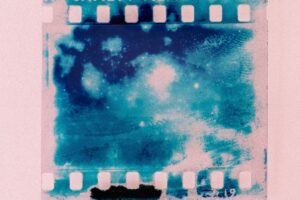









コメントを残す